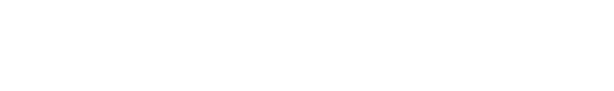すり抜けはヒヤッとする
賛否が分かれるバイクの「すり抜け」の法的解釈
バイクに乗る上で、渋滞時などに前方の車列の間を通り抜ける「すり抜け」は、ライダー間で賛否が分かれる行為です。
道路交通法において「すり抜け」という行為自体を直接的に定義し、禁止する明確な規定はありません。
しかし、その方法によっては、複数の法令違反となる可能性があるため、安易に行うことは非常に危険です。
すり抜けを行う際は、単に「禁止されていないから大丈夫」と考えるのではなく、法的なグレーゾーンにあることを十分に理解し、常に安全に最大限配慮する必要があります。
追い越し違反(追越し禁止場所)
道路の右側部分は追い越しのための車線ですが、交差点の手前30m以内や、追い越し禁止の標識がある場所で追い越しを行うと違反となります。
進路変更禁止違反
車線変更が禁止されている場所での急な進路変更や、進路変更時の合図不履行は違反です。
安全運転義務違反
著しく危険な速度や方法で行い、他車に危険を及ぼすと判断された場合、この義務違反に問われる可能性があります。
すり抜けのメリット・デメリット
すり抜けは、ライダーにとって大きな利便性をもたらす一方で、危険性も伴います。
すり抜けを行うメリット
最大のメリットは、「移動時間の短縮」と「エンジンのオーバーヒート防止」です。
渋滞の列に長時間留まることなく前進でき、特に通勤など時間に追われるシーンで効果を発揮します。
また、空冷エンジンを搭載したバイクは渋滞でオーバーヒートするリスクがありますが、すり抜けで風を当てることでこれを防ぐ目的もあります。
すり抜けのデメリットとリスク
デメリットは、「事故のリスク増大」に尽きます。
車列の脇を通過する際、予期せぬドアの開閉や、急な車線変更を行う四輪車との接触事故のリスクが格段に高まります。
特にドライバーからはバイクの存在が見えにくいため、ヒヤリとする瞬間が多く発生します。
安全に走行するためのマナーと技術
すり抜けを行う場合、法的解釈に加え、周囲への配慮と高度な運転技術、そしてマナーが求められます。
四輪車への配慮を最優先したマナー
すり抜けを行う際は、極低速でゆっくりと走行することが鉄則です。
歩行者が横断する可能性がある場所や、交差点付近では、すり抜けを避けるか、一度完全に停車して安全を確保すべきです。
四輪車のドライバーの死角に入らないよう、ヘッドライトを点灯し、できる限り車体との間にスペースを確保することがマナーです。
常に停止できる速度と技術
すり抜けは、いつでも瞬時にブレーキをかけて停止できる極めて低い速度で行う必要があります。
ハンドルやミラーが車に接触しないよう、車幅感覚を常に意識し、進路変更の際は必ずウインカーを早めに出して意思表示を行ってください。
「もしかしたらドアが開くかもしれない」という危険予測を常に怠らないことが、事故を防ぐための最も重要な技術であり、マナーの基本となります。